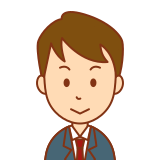
確定拠出年金(DC)をよく聞きますが、確定給付年金(DB)という言葉も聞きます。この違いは何ですか?

リスクを取るのが、「社員(個人)」と「会社」のどちらかということです。
確定拠出年金(DC)とは
確定拠出年金の「DC」とは、「Defined Contribution」で直訳すると「決まった掛け金」です。
DCと聞くと、自分で商品を運用してというイメージがあると思います。
DCは「会社が社員へ決まった掛け金を出しますよ」という制度です。
確定給付年金(DB)とは
似た言葉で「確定給付年金(DB)」という言葉もあります。
「DB」は「Defined Benefit」で直訳すると「決まった利益」です。
DBは「会社が拠出・運用して、社員への退職金の支払を保証しますよ」という制度です。
この2つの大きな違い
上記の通り「リスクを取るのが、『社員(個人)』と『会社』のどちらか」ということです。
運用してマイナスになった場合、DCであれば「個人」、DBであれば「会社」がリスクを取ります。
例えば、原資2,000万円を拠出・運用した結果、1,500万円になったとします。
(原資2,000万円ー運用結果1,500万円=▲500万円)
【DCの場合】
▲500万円分は、個人の負担となります。今後の生活を考え直す必要があるかもしれません。
【DBの場合】
▲500万円分は、会社の負担となります。労使と締結した協定や退職金規程に沿った退職金額を社員へ払う必要があり、赤字分は会社で補填する必要があります。
近年DCの会社が増えているのはなぜか
以前はDCではなく、DBの会社が主流でした。
しかし、高度経済成長期ではなく、少子高齢化社会の現在の日本においては、
会社が退職金を補填するのは、「リスクがある」と舵を取ったと言えます。
上記で、▲500万円の例を出しましたが、定年退職者の数は今後も増えていくことは間違いありません。
仮に、毎月2人の方が定年退職し、運用結果▲500万円だった場合、1億2,000万円(▲500万円×24人/年)の赤字を会社は抱えることになり、本業以外での損失が非常に大きくなります。
これでは会社としてはいくら利益を出しても、将来の見通しが立てません。「確定拠出金(DC)」へシフトすることで、将来の見通しを立てる会社が増えているということです。
「確定拠出年金(DC)」のメリット
これまでの話を聞くと、社員(個人)にとって、ネガティブなイメージですが、
運用次第で本来会社からもらう退職金よりも大きな額を得ることもできる可能性があります。
また、DBは一般的に「勤続年数」に応じて退職金額が決定され、転職等で退職すると当然ですが「勤続年数」は「1年目」からリセットされます。
DCの場合、「等級」に応じて掛金決定されて積み立てますが、転職先にDC制度があったり、idecoを活用したりすることで引き継ぐことができます。
つまり、「転職」という視点で考えれば、退職金の影響は少なくなったとも考えることもできます。
結論
- 「確定拠出年金(DC)」は「個人」がリスクを取り、「確定給付年金(DB)」は「会社」がリスク取る。
- 近年では、会社が以前のようにリスクを取れなくなっているため、「掛金」を拠出する「確定拠出年金(DC)」へ移行する会社が増えている。
- 「確定拠出年金(DC)」は、良くも悪くも個人の運用次第
- 「確定拠出年金(DC)」は、転職先のDCやidecoに引き継ぐことができるため、転職時の退職金の影響は少なくなった。
最後に
良いか悪いかは別として、生活に投資が関わってくる時代になりました。
自分の判断に責任を持てるようになりたいですね。
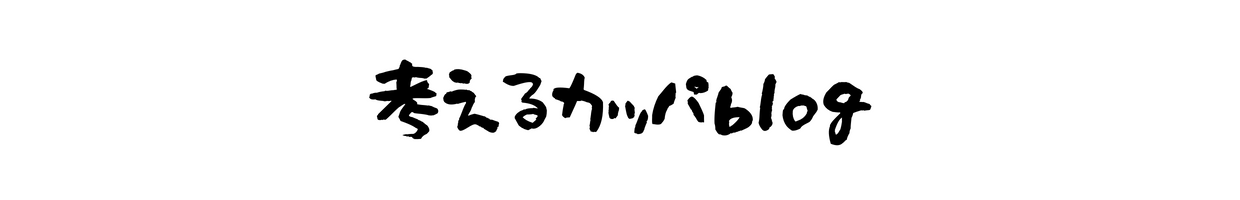

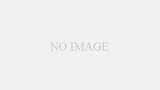
コメント